ごきげんよう。
「ケンタロウのファミリーファイナンス」へようこそ。
※ファミリーファイナンスについて知りたい方は👉コチラより♪
デリバリーキッチンについて知りたい方は👉コチラより♪
「どうして毎月お金が足りないんだろう?」
「節約してるはずなのに、貯金がちっとも増えない…」
そんなモヤモヤを抱えながら、検索にたどり着いたあなた。
僕もまったく同じところからスタートしました。
子どもが生まれて家計がガラッと変わり、何とかしなきゃと思ったときに行き着いたのが“貯金と節約を両立する”という考え方でした。
実は、ちょっとしたコツを取り入れるだけで、月に5万円も浮かせることができたんです。
大きな我慢や根性はいりません。むしろ「賢く手を抜く」くらいがちょうどいい。
この記事では、忙しいパパ・ママでもできる具体的な家計の見直し方法や、日常でムリなく続けられる節約の工夫をわかりやすくまとめました。
僕自身のリアルな家計改善の体験も交えて紹介するので、読みながら自分の家庭に合うやり方を見つけてもらえたら嬉しいです。
このあと、すぐに始められるチェックリストも紹介しています。
ぜひ最後まで読んで、あなたの家計に“安心の余白”をつくってみてくださいね。
なぜ“貯金と節約”は両立しづらいのか?
節約しているのに貯金が増えない理由
節約しているのに貯金が増えない──これは多くの家庭がぶつかる悩みです。
特に共働きや育児中の世帯では、時間も気力も限られているため、食費や光熱費を抑えても思うようにお金が残らないことがあります。
理由は明確で、節約と貯金は「同じ方向を向いていないこと」が多いからです。
たとえば「安いから」とまとめ買いした食材を使いきれずに廃棄してしまったり、ポイント還元につられて必要のない買い物をしたり──。
節約しているつもりが、結果的には支出が増えているというケースは少なくありません。
さらに、節約を意識しすぎると「これくらいはいいか」という気の緩みが生じて、突発的な出費への耐性が低くなることも。
「節約=我慢」になってしまうと、続かない上に満足感も得られず、結果的に貯金にもつながりません。
だからこそ、僕が実感したのは「節約の目的を明確にすること」の大切さ。
単に支出を減らすのではなく、貯金という目的に向けて支出をコントロールしていく意識が必要なんです。
家計が赤字になる“見えない出費”とは?
家計簿をつけていても、なぜか毎月の予算がオーバーする…。
それは「見えない出費」が原因かもしれません。
例えば、育児中の家庭ではおむつやミルク、洋服の買い替えといった「定期的だけど毎月ではない」出費が重なりがちです。
これらは月々の予算に組み込まれにくく、気づけば赤字になっていることも。
また、帰省やプレゼント、急な外食など、予定外のイベント支出も見落としがちです。
これらを家計簿上で「特別費」として管理できていないと、「節約したのに残らない」現象が発生します。
つまり、節約だけでなく「予算に含めるべき費用」をきちんと可視化しないと、貯金にはつながらないということ。
僕も以前は、こうした出費を把握できておらず、毎月の振り返りで驚かされていました。
現在は、年単位・季節単位で発生する支出をあらかじめリスト化し、家計アプリで管理しています。
こうすることで予算に余白ができ、精神的にもゆとりを持って家計を回せるようになりました。
意外と多い「節約疲れ」の落とし穴
節約に夢中になっていた頃の僕がぶつかった最大の壁──それが「節約疲れ」です。
細かい家計簿、クーポンの検索、チラシチェック、電気のつけっぱなしの指摘…。
日々の生活が「お金のこと」に縛られ過ぎると、次第にストレスが溜まっていきます。
これは特に、子育て中の家庭にとって深刻で、家庭内の雰囲気にまで影響することもあります。
節約疲れを感じると、どこかで「爆発」が起きます。
例えば、「今日はもういいや」とコンビニでの無駄遣いが増えたり、ネットショッピングで散財してしまったり…。
つまり、節約は頑張りすぎると逆効果になってしまうんです。
だからこそ重要なのは、「手を抜くべきところは抜く」こと。
我が家では、スーパーのチラシに振り回されるのをやめ、決まった曜日にまとめ買いをするスタイルに変えました。
それだけで時間も心もラクになり、節約に対するストレスがぐっと減りました。
貯金も節約も「長く続けること」が大切です。
そのためには、完璧を目指すより、ほどよいズボラさが武器になるんだと、僕は強く感じています。
ここまで読んで、「じゃあ実際にどうやって月5万円も浮かせたの?」と気になってきた方も多いはず。
次は、僕が実際に取り組んで「貯金と節約を両立させた」リアルな体験をお話しします。
月5万円浮かせた!僕の“リアルな家計改善ストーリー”

子どもが生まれて気づいた家計のピンチ(※育児との両立を含める)
「育児が始まった瞬間、家計は一気に緊迫する」──これは大げさではなく、僕が実際に感じたリアルな現実です。
2024年9月10日に息子が生まれてからというもの、これまでの生活費では全く足りなくなりました。
おむつやミルク代はもちろん、予防接種、ベビーグッズ、洋服の買い替え…。
気づけば月々の出費は軽く5万円以上も増えていたんです。
育児休業中の収入減に加えて、慣れない育児と仕事の両立で心にも余裕がなくなり、気がつけば「何に使ったのか分からない出費」が毎月積み重なっていました。
このままではまずいと思い立ち、僕がまず取り組んだのが“家計の可視化”でした。
感覚で動いていた家計を、数字として把握することで「どこにムダがあるのか」が見えてきたんです。
やったこと① 固定費の見直し
最初に手をつけたのは、毎月の支出の中でも特に効果が大きい「固定費」の見直しです。
ここを変えるだけで、毎月自動的に節約ができる仕組みを作れます。
具体的には、次の3つを見直しました。
まず、スマホ代。
キャリアから格安SIMに乗り換えたことで、夫婦2人分で月10,000円近く浮きました。
次に、電気とガスのプランを一括見直し。
比較サイトでシミュレーションして切り替えるだけで、年間約18,000円の節約に成功。
そして、意外と見落としがちな「サブスク」。
動画サービスや定期購入アプリなど、なんとなく契約していたものを棚卸しして、使っていないものは即解約。
これだけで月2,000〜3,000円の固定費を削減できました。
固定費の削減は、一度見直すだけで効果が続く「家計の筋トレ」みたいなもの。
手間は最初だけで、節約の自動化が実現します。
やったこと② 食費の無駄を見える化
次に取り組んだのが食費の最適化です。
育児中はついコンビニやスーパーの惣菜に頼りがちですが、これが想像以上に家計を圧迫していました。
僕が始めたのは、1週間ごとの献立計画。
週末に冷蔵庫の中身をチェックしてから買い物リストを作るようにしたことで、食材の重複買いや廃棄が激減しました。
さらに、買い物の頻度も週2回に固定。
無駄な“ついで買い”を防げるようになりました。
それに加えて、使いかけ食材の消費を優先する「使い切りレシピ」を習慣に。
これだけでも、月に5,000〜7,000円の削減が見込めます。
食費を見直すことで、節約だけでなく「栄養バランス」や「家族の健康」にも好影響が出てきました。
外食を減らし、自炊が中心になることで、息子の離乳食も安心して作れるように。
これって一石三鳥じゃないですか?
やったこと③ 保険の無料相談を利用
最後に見直したのが保険です。
結婚当初に加入して以来、ずっと放置していた生命保険や医療保険。
内容もよくわからず、月に2万円以上支払っていました。
そこで、思い切って無料の保険相談サービスを活用。
担当の方が家計の状況や子育てプランに合わせて最適なプランを提案してくれたことで、保障内容はそのままで、月額で約7,500円の削減に成功しました。
特に印象的だったのが、「保険は家族のライフステージごとに見直すべき」というアドバイス。
まさに今の僕に必要なタイミングだったと感じています。
不安だった“営業っぽさ”もなく、むしろこちらの悩みに丁寧に寄り添ってくれて、「もっと早く相談すればよかった…」というのが率直な感想です。
📌 固定費や保険をプロと一緒に見直すことで、無理なく家計にゆとりが生まれます。 僕も実際に使って「こんなに変わるのか」と驚きました。
▼▼▼▼過去に紹介した保険の無料相談サービスブログを見る▼▼▼▼
ベビープラネットの口コミ・評判を徹底調査!学資保険や子育て世帯のための最適プランとは?
保険のトータルプロフェッショナルとは? 失敗しない保険の見直しのコツを徹底解説!
保険ランドリー×無料相談で家計改善!忙しい共働き家庭に人気の理由とは?
baby planetはどんな人に向いてる?がん保険の専門相談サイトを徹底解説!
ここまでの工夫で、気づけば月5万円以上の支出が削減できていました。
そして、何より大きかったのは、家計に「仕組み」ができたことで、節約が自然に回るようになったことです。
次の章では、僕が今も実践している「ムリなくお金が貯まる7つのコツ」を詳しく紹介していきます。
忙しい中でも続けやすい工夫ばかりなので、ぜひチェックしてみてください。
賢い人がやってる!ムリせずお金を貯める7つのコツ

コツ① 予算を“項目ごと”に決めておく
家計がうまく回らない理由の多くは、「お金の流れが見えていないこと」です。
収入は決まっていても、支出がどこにどれだけかかっているか把握できていないと、結果的に貯金どころか赤字になりがち。
僕が取り入れて効果を感じたのは、食費・日用品・交際費など「用途別」に月の予算を設定することでした。
たとえば
「食費は35,000円」
「日用品は月5,000円」
といった具合に最初から仕切っておくと、予算内で収める意識が自然と芽生えます。
特に、スマホの家計簿アプリを活用すると、予算超過のタイミングもすぐにわかるので便利です。
手元で管理できることが、モチベーションにもつながります。
コツ② キャッシュレス決済で家計を可視化
現金払いでは気づきにくい出費の流れも、キャッシュレス決済なら自動で記録されるので、家計の見える化には欠かせません。
僕は特に、クレジットカードとスマホ決済(PayPay、楽天Payなど)を家計管理のツールとして活用しています。
アプリ連携でグラフ表示されるため、「何にいくら使っているのか」が一目瞭然。
見えることで、「今月ちょっと使いすぎてるな」と気づき、セーブできるようになりました。
また、キャッシュレスはポイント還元の恩恵も大きく、実質的に節約になるケースも少なくありません。
ただし、「ポイントを貯めるために買い物をする」のは本末転倒なので要注意です。
コツ③ おトクなふるさと納税を活用
正直、僕も最初は「ふるさと納税って面倒そう…」と思っていました。
でも、始めてみたら意外と簡単で、しかも食費や日用品の節約になるうえ、税金の控除まで受けられるので、やらない手はありません。
たとえば、我が家では「お米」「冷凍ハンバーグ」「トイレットペーパー」など、普段から使う消耗品を返礼品として選んでいます。
結果的にスーパーでの買い物が減り、月5,000円以上の節約になった月もありました。
確定申告が不要な「ワンストップ特例制度」を使えば手続きも簡単。
まだ、利用したことがない人は、ぜひ今年からチャレンジしてみてください。
コツ④ セールやポイントに惑わされない買い方
「セールだから買う」は浪費の入り口。
このワナには、僕も何度も引っかかってきました。
安くなっていたからとまとめ買いした調味料やお菓子が賞味期限切れで廃棄…なんてことも。
大事なのは、「買いたいから買う」のではなく「必要だから買う」習慣を身につけること。
セールはあくまで手段であって、目的ではありません。
たとえ割引率が高くても、本当に必要なもの以外には手を出さない。
このルールを守るようにしてから、買い物の精度がぐっと上がりました。
それに、ポイントも同じ。
使うことで生活にプラスになる場合だけ活用し、ポイント目的で浪費することがないよう意識しています。
コツ⑤ お金を使う“優先順位”を家族で話し合う
節約を成功させるうえで、「お金の価値観をすり合わせる」ことが非常に大事です。
特に夫婦で生活費を共有している場合は、支出の優先順位にズレがあると、無駄遣いやモヤモヤの原因になります。
我が家では月に1回、家族で「今月何にお金を使いたいか」を話す時間をつくっています。
子どものお祝い、日帰りの家族旅行、新しい家具など、未来にお金を使うイメージが共有できると、日々の節約も前向きに取り組めるようになります。
この「話す時間」は、家計の管理だけでなく、家族の絆や方向性の確認にもつながると感じています。
コツ⑥ 外食・デリバリーの賢い使い方
共働きや育児中の家庭では、外食やデリバリーを完全にやめるのは現実的ではありません。
だからこそ、「頻度と目的をコントロールする」ことが大切です。
我が家では、「週に1回だけ」「月末のご褒美デーだけ」など、明確なルールを決めて外食を楽しむようにしています。
また、クーポンアプリやテイクアウト割引を活用すれば、同じ金額でもちょっと豪華に楽しめます。
忙しい中での“ご褒美外食”は、家族にとっての大切なリフレッシュ時間。
節約しすぎず、メリハリをつけることで、生活の満足度もアップします。
コツ⑦ 保険やサブスクの見直しを習慣にする
最後のコツは、「定期的な支出の棚卸しを習慣にすること」。
僕も以前は、放置された保険や使っていないサブスクで毎月1万円近く無駄にしていました。
まず保険は、ライフステージが変わったら必ず見直すべきです。
無料相談サービスを使えば、家計や子育て状況に合った提案をしてもらえるので安心です。
サブスクも同様。動画・音楽・宅配系などは、使っていないのに契約が続いているパターンが多いです。
定期的に明細をチェックし、「本当に必要か?」を自問するだけで、固定費は大きく変わります。
📌 我が家も保険の見直しだけで年間9万円以上の節約に成功しました。
「今のままで本当にいいのかな…」と感じたら、プロに相談してみると道がひらけるかもしれません。
▼▼▼▼家計に合った保険の無料相談はこちら▼▼▼▼
ベビープラネットの口コミ・評判を徹底調査!学資保険や子育て世帯のための最適プランとは?
保険のトータルプロフェッショナルとは? 失敗しない保険の見直しのコツを徹底解説!
保険ランドリー×無料相談で家計改善!忙しい共働き家庭に人気の理由とは?
baby planetはどんな人に向いてる?がん保険の専門相談サイトを徹底解説!
ここまでご紹介した7つのコツは、どれも大きな負担なく、今すぐに始められるものばかりです。
とはいえ、「うちの家庭に合うか不安…」「他の人はどうしてるの?」と思う方もいるかもしれません。
次は、実際に読者の皆さんから多く寄せられた「貯金と節約のQ&A」にお答えしていきます。
ちょっとした疑問がスッキリすれば、より前向きに家計と向き合えるはずです。
読者の疑問に答えます!貯金と節約Q&A
Q1:どこから見直せばいいかわからないんですが…
最初に見直すべきは「固定費」と「支出の流れの可視化」です。
これは多くの家庭に共通する“無駄が潜むポイント”でもあり、しかも改善のハードルが低い部分でもあります。
たとえば、僕が見直しを始めたときは、毎月なんとなく引き落とされていたスマホ代、サブスク料金、不要な保険などがザクザク出てきました。
これらは一度見直すだけで「何もしなくても毎月の出費が減る」、いわば家計のダイエットメニューです。
また、家計簿を「書くことがゴール」にせず、支出を“見える化”するための手段として捉えることも重要です。
アプリを使えば、レシートを撮るだけで自動分類されるものもあるので、手間をかけずに見直しの第一歩を踏み出せます。
「全部一気にやろう」とせず、まずは固定費1つだけでも見直してみる。
それだけでも気持ちが軽くなり、次の行動につながる感覚を得られます。
Q2:節約すると生活の満足度が下がる気がします
この質問、よくわかります。
僕も以前は「節約=我慢」「生活レベルを下げること」だと思っていました。
でも、実際はその逆でした。
大事なのは「満足度の低い支出」を見直して、「本当に価値を感じること」にお金を使うバランスを整えることです。
たとえば、惰性で続けていた飲み会やコンビニスイーツをやめて、その分で家族と過ごす外食の質を上げたり、おうちカフェのアイテムを揃えたり。
節約によって“本当に好きなこと”にお金を使えるようになると、生活の満足度はむしろ上がりました。
節約とは、「お金の優先順位を整えること」なんだと実感しています。
だからこそ、今の暮らしを大きく変えなくても、価値ある選択ができるようになるんです。
Q3:保険の見直しってどう進めればいい?
保険は「入りっぱなし」「なんとなく加入」が一番の落とし穴です。
特に子どもが生まれたばかりの家庭や、ライフスタイルが変わったタイミングでは、一度立ち止まって確認すべきタイミング。
僕自身も、結婚と出産を機に保険の内容を見直しました。
といっても、いきなり保険ショップに行ったり、資料請求をするのは正直しんどい…。
そんなときに使ってよかったのが「無料の保険相談サービス」です。
こちらの家計状況や希望を丁寧に聞いた上で、過不足のないプランを提案してくれます。
実際、月々約7,500円の削減になり、無理に勧誘されるようなこともなかったので、安心して任せられました。
📌 我が家もこのサービスで、月7,000円以上の固定費が削減できました。
「うちの保険、ムダがあるかも…?」と思ったら、まずは試してみて損はありません。
▼▼▼▼無料でできる保険の見直しサービスはこちら▼▼▼▼
ベビープラネットの口コミ・評判を徹底調査!学資保険や子育て世帯のための最適プランとは?
保険のトータルプロフェッショナルとは? 失敗しない保険の見直しのコツを徹底解説!
保険ランドリー×無料相談で家計改善!忙しい共働き家庭に人気の理由とは?
baby planetはどんな人に向いてる?がん保険の専門相談サイトを徹底解説!
さらに、見直しのポイントは「更新時期」「保障の重複」「ライフイベントへの対応」です。
とくに医療保険・学資保険は内容の違いが分かりづらいので、プロの意見をもらえるのは非常に心強い存在です。
こうした読者のリアルな疑問は、まさに家計改善の“第一歩”です。
とはいえ、節約に正解はありません。
大切なのは、あなたの家庭にとって“ちょうどいいスタイル”を見つけること。
次の章では、節約を「我慢」ではなく「前向きな習慣」に変えるための、考え方や工夫をご紹介します。
「節約=我慢」じゃない。家庭に合ったスタイルを見つけよう

他人と比較しないことが長続きのコツ
節約を続けるうえで、一番の敵は「他人との比較」です。
SNSを開けば、ミニマリストの徹底した節約術や、毎月○万円貯金している人の投稿があふれていますよね。
でも、こうした情報を鵜呑みにしてしまうと、自分のペースや状況に合わない方法を無理にマネしてしまい、かえって疲れてしまうことがあります。
たとえば、僕の家庭は共働きで1歳の娘を育てています。
正直、毎日自炊を完璧にこなすのは難しいし、外食や宅配に頼る日もあります。
けれど、「この家のスタイルに合ったペースでやる」と決めてからは、節約がプレッシャーではなく、自然と生活の一部になりました。
大切なのは、「うちはうち、よそはよそ」という視点を持つこと。
他人の節約法はあくまで参考程度に留め、自分たちの生活と照らし合わせて“できる範囲”を選ぶのが、節約を長く続ける秘訣だと感じています。
我が家ルールで“楽しむ節約”を習慣に
節約というと、どうしても“節制”や“我慢”のイメージが強いかもしれません。
でも、実は工夫次第で「楽しい時間を生み出すきっかけ」にもなるんです。
我が家では、「おうち映画の日」を月1回開催しています。
映画館に行く代わりに、家でポップコーンを作って、ちょっと贅沢なお菓子とドリンクを用意して、リビングをシアターに。
外出よりもずっと安上がりなのに、子どもも大喜びで、毎月の楽しみになっています。
また、休日は「予算1,000円以内でピクニックランチチャレンジ」など、あえて制限を設けることで、節約を“遊び”に変える工夫もしています。
ルールを家族で共有して取り組めば、節約が協力し合うプロジェクトに変わるんですよね。
節約を苦しいものにしないために、僕たちが意識しているのは、「あれはやめよう」ではなく、「これはやろう」という前向きな発想です。
お金をかけなくても豊かに感じられる経験を増やすことが、家計と心の両方のゆとりにつながっていきます。
節約は我慢ではなく、「心地よい暮らし」を作るための手段。
そのためには、他人の正解に振り回されず、家庭に合ったやり方を見つけることが何よりも大切です。
いよいよ次は、ここまでのポイントをまとめて、“お金と心の両方にゆとりが生まれる生活”への一歩を一緒に振り返ってみましょう。
まとめ~月5万円のゆとりは、心のゆとりにもつながる~
今日からできる3つの一歩
貯金と節約を始めるのに「完璧な準備」は必要ありません。
今日から、今すぐできる小さな一歩を積み重ねることが、家計の安定につながります。
まず最初にやってほしいのは、「支出の見える化」です。
特別な知識やツールがなくても、スマホの家計簿アプリを使えばすぐに始められます。
どこにお金が流れているかを把握するだけでも、不要な出費に気づけるようになります。
次に、固定費の見直しをしてみてください。
特に保険や通信費、サブスクなどは、無意識のうちにお金が流れ続けている項目。
ここを見直すだけで、「頑張らなくても減る支出」を作れます。
そして、もう一つ。
節約に“自分たちらしさ”を取り入れてください。
ルールや制限ではなく、家族が楽しめる方法で取り組むことで、無理なく続けることができます。
おうち映画や自作おやつの日など、楽しみながら取り組む工夫が、節約を“前向きな習慣”に変えてくれます。
最後に:貯金と節約の本当の目的を見直してみよう
この記事を通してお伝えしたかったのは、「貯金と節約は、生活を苦しくするものではない」ということです。
我慢ばかりの節約では、いつか疲れてしまいます。
でも、「自分たちの理想の暮らしをつくる手段」として捉えることで、貯金と節約はとても心強い味方になります。
月に5万円浮かせることができたとき、僕が感じたのは“お金の余裕”よりも、“心の余裕”でした。
急な出費に慌てることも減り、子どもとの時間にも集中できるようになりました。
お金の不安が減ることで、家族との会話が増えたり、日々の選択に自信が持てたりするようになります。
つまり、家計の見直しは、単なる数字の話ではなく、「人生の質」を整える第一歩でもあるんです。
もし今、「うちも何とかしたいけど、何から始めたらいいか分からない」と思っていたら、まずは一つ、今日紹介した中から試してみてください。
小さな変化が、確かな成果につながっていきます。
貯金と節約は、がんばるものではなく、整えるもの。
あなたの家計にも、ちょうどいいスタイルがきっと見つかるはずです。
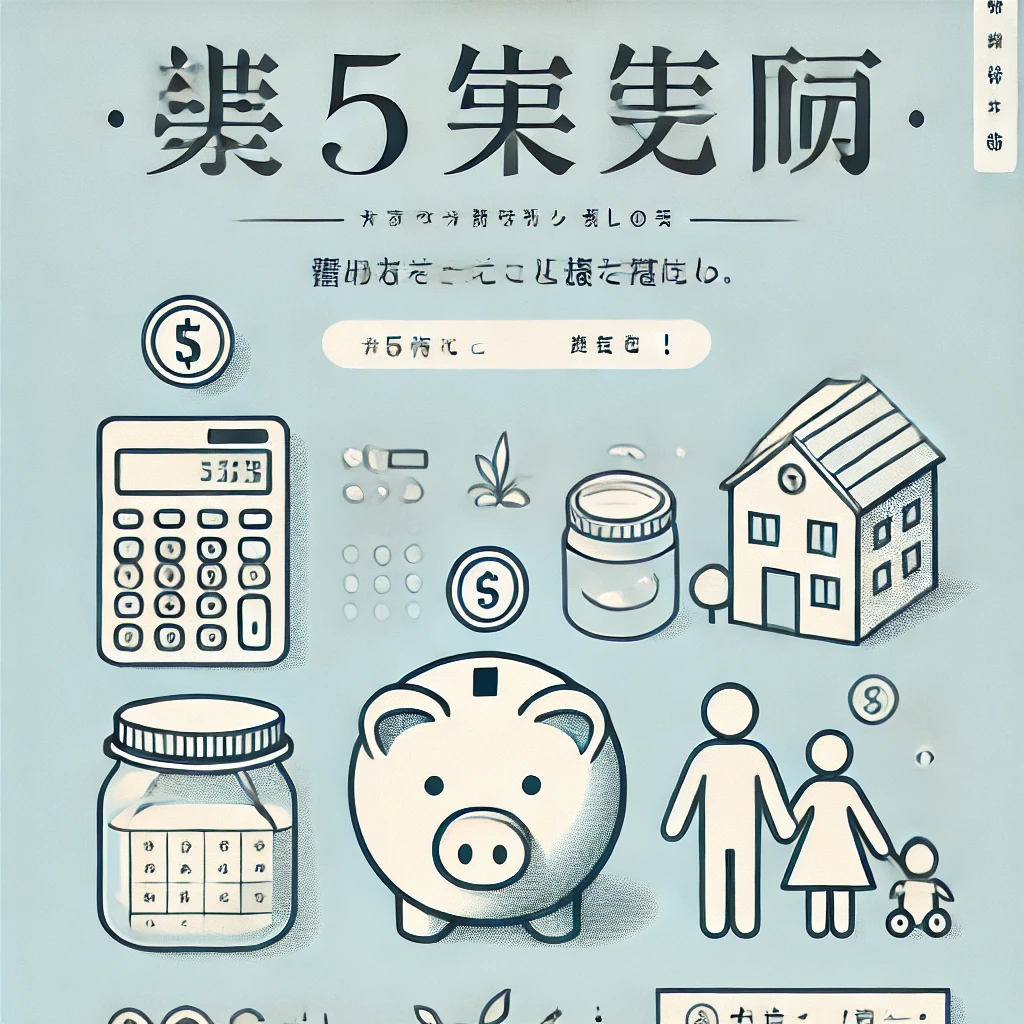


コメント